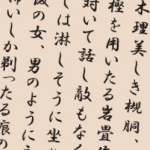男女関係ぬきの『或る女』はどうだろうか
本作『或る女』は、有島武郎の長編小説。主人公である葉子は、非常に現代的かつ蠱惑的な女であって、倉地、木村はもとより、作中で名前が挙がるほどの男は皆、彼女の虜になってしまう。小説でそう創られているのだからそうだというしかないのだが、そんな女が実際どれほどいるだろうかとも思う。葉子のように、感情や行動の振幅が大きくて、何かにつけて目立ってしまう人間というのは、男女を問わずいるものだ。だが、それ以上に人を惹きつけるというのは少々ピンとこない。管理人がそう感じるだけかも知れないが。
物語を丸呑みする男女関係
以前に、政治性の強い小説の類は政治パンフレットのようなもので好きになれないと書いたことがあるが、男女関係についてもこれと似たようなことが言える(他にもう一つ、宗教がある)。およそ人間関係が問題になる小説で男女関係がまったくオミットされるのも不自然であるが、必要以上に入り込んでくると、作中にある他のテーマや何やらをすべて丸呑みにしてしまう点では政治と同じだ。
なぜこんな奇妙な人間関係が成立するのかという疑問が、すべて男女関係で説明されてしまう。ほとんどあり得ないような心理の変化が、男女関係から簡単に導かれてしまう。それはあるいは(少なくとも作者の頭の中では)真実なのかも知れないが、現実でそれが起こるならともかく、フィクションでそれが起こると、興ざめとは言わないまでも、物足りなさを感じてしまう。
欲望と諦観、優越と不安、自立と依存
本作の倉地は、一癖あることは確かであるが、仕事を放擲した挙句やすやすと違法行為に手を染めるほど向こう見ずな男には見えない。葉子は、見掛けほど単純な人物ではないはずだし、男に入れ揚げるのとはほど遠いくらい男の扱いに慣れた女である。そういう二人がくっついてズブズブと深みにはまってしまうのを、フィクションの枠内で説明するのは難しい。それが男女関係ということで説明されてしまうのだ。
もちろん、本作は男女関係一本やりの作品ではない。欲望と諦観、優越と不安、自立と依存、そうした複雑な要素が絡み合っている。そして、明(と言っても陰りを帯びているが)から暗への変転、あるいは暗が明を突き破って出てくる様は、確かに圧巻である。それならば、むしろ倉地との関係などは何分の1かに圧縮して、他の要素総動員で徹底的に葉子という人間を解体して欲しかった。
作中人物に感情移入するとは
さて、本作の後編、日本に戻ってからの葉子は下降一直線である。最後は、(病気の影響があるにしても)ほとんど狂い死にという有様である。死に体の葉子はもとより、バラバラと散ってゆく周囲の男どもにも、とても感情移入はできないな……、と思っていたところ、そもそも管理人は作中人物に感情移入することなどあるのだろうか、と思い当たった。
管理人は、作中人物を応援したり、叱ったり、イライラしたり、愛想を尽かしたりはするが、作中人物と同化して、その視点でものを見るようなことはない。せいぜい、似たような境遇に置かれたらどうするだろうか、と考えるくらいのものである。あるいは、その程度のことを「感情移入」と呼びならわしているのだろうか。本作とは関係ないことながら、少々気になった。
或る女
有島 武郎 作
新潮社(新潮文庫)