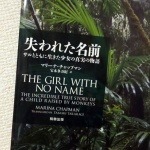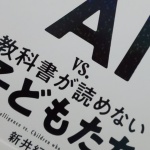アマゾン少数民族の言語と宇宙『ピダハン』
ピダハンとは、アマゾンの奥地に暮らす400人ほどの少数民族。本書『ピダハン』は、キリスト教の伝道師であった著者が、30年がかりで彼らの独特の文化と言語を研究した記録だ。著者は、その間何度も、家族と共に彼らの居住地を訪れ、彼らと共に生活し、研究を進める。いわゆるフィールドワークなのだが、ものの見方、考え方があまりに違いすぎていて、いちいち彼我の違いを見せつけられる。
ピダハンは、道具類を作るなど、物を加工することはまずしない。作るにしても、あえて長くもたせるようなものは作らない。目をひくのは、狩りに使う弓矢と悪霊祓いのネックレスくらいだ。ブラジル製のカヌーを使いはするが、自分たちで作ろうとはしない。彼らは、外の世界の知識や習慣をやすやすと取り入れない。そして、彼らの生活と思考をつらぬく、ある「文化の原則」……。
リカージョンのないピダハン語
本書の中で最も注目すべきなのは、何とも独特なピダハンの言語である。著者によれば、ピダハン語には、数や色を直接に表す言葉すらないという。数や色と言えば、海外旅行の前ににわか仕込みでいの一番に覚えるような言葉である。それがないとは、どういうことか。それで実用になるのか、アマゾンの過酷な環境を生き抜けるのか、という気もするのだが……。
言語学的には、リカージョン(再帰)がないということが、大問題であるようだ。リカージョンとは、例えば、「魚を獲った男が家にいる」のように文の中の名詞の位置に、それ自体が文で構成された名詞句が入る、というような入れ子構造のことだ。これによって、限られた単語や文法から、無限に複雑な文を作ることができる。従来の言語学の常識からすれば、このようなリカージョンこそが人間言語の固有の要素であるはずだった。
「欠けている」という認識は正しいか
ただ、著者も指摘するように、そもそも「欠けている」という理解の仕方が正しいのかという問題はある。実際、ピダハン語では、彼らの「文化の原則」からリカージョンが禁じられているが、意味的にリカージョンと同等となるような表現を作る方法はあるのだという。もっと言えば、欠けているところばかりが目につくとしても、我々は我々の方が欠けていることには気づきようがない。文化相対主義を気どるわけではないが、彼らには彼らの確固たる世界があるのだろう。
あるいは、ピダハン語も、見かけほど特異なものではないのかも知れない。実際、アメリカ人である著者もピダハン語をマスターできたのだし、言語学的にいくら違っていてもその違いをそれなりに認識し、理解することもできる。言語の文法は必ずしも普遍的ではないが、例えばリカージョンのある形に成型されやすい、というくらいには人間の脳の言語鋳型は普遍的であるということだろうか。
ピダハン世界の奥底には何がある
著者は、30年にわたる研究、あるいは共同作業、あるいは共同生活の末、もともと伝道師としてピダハンの居住地に入りながら、遂には無神論となってしまう。そして、かつて著者を殺すと脅したピダハンの中には生涯最高の友に数えられる者がいる、と言うに至る。まさに、ピダハンの世界にペッタリと嵌ってしまったわけだ。
ただ、それでもやはり、著者は西洋人である。長くても1年でピダハン居住地を離れるし、生活スタイルもまったく現地風というわけではなく、生活必需品は飛行機で送ってもらう。送られてきたサラダを食べていると、「ピダハンは葉っぱを食べない。だからおまえはおれたちの言葉がうまくないんだ。」などと言われてしまう。そう考えると、著者ですら、彼らの世界の奥底には達していないのかも知れない。もっとも、そこまで行ってしまえば、本書のような本は書けなかっただろうが。
ピダハン 「言語本能」を超える文化と世界観
ダニエル・L・エヴェレット 著
屋代 通子 訳
みすず書房